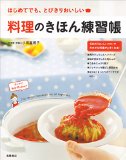はじめてでも、とびきりおいしい「料理のきほん練習帳」 小田真規子著 シリーズ累計35万部突破。料理レシピ本大賞、入賞本。
この本を見れば、たしかに思います。
どうしてお料理本は、ハンで押したように同じような書き方をしたものが多いのかと。
使う材料、分量、手順。
それで伝えられることは実はわずかで、それだけで美味しい料理を作るキモを伝えるのは、
なかなか難しいことなのではないかと。
もちろん、そういう料理本があってもいいと思います。
対象とする読者に、ある一定の実力があり、自分自身のやり方を持っていたり、お料理のキモを自分で知っている、とか、
また書き手に、どうすれば美味しくなるのかご自分で研究して学ばれないと本当のお料理はできない、などの意志があるとか、
いろいろな考え方で、そういう書き方になるということはあると思います。
でも、周りがみんなそういう書き方をしているから、という理由で同じような書き方になるなら、
少しもったいない。
その料理の作り方が分かりやすく伝わるように、というような思いで自由に工夫して書かれたもの、
作り手の、世の中や読者に貢献しようという思いだったり、温度の伝わってくるようなものが、読者としては、やはり読みたい。
例えば、私は小学生の時に有名ホテルのコックさんから、オムレツの作り方を習い、
(テレビで。(笑))
いまもフワッフワなオムレツを作れるのですが、
それをレシピっぽく書いてみるとこんな感じ。
材料。 卵2個、塩、サラダ油 各少々。
① 卵をボールに割り入れ、塩を入れよく解きほぐす。
② フライパンにサラダ油をひき、強火でよく熱し、①を入れる。
③ 固まってきた卵の外周からお箸でかき混ぜ、スクランブルエッグの要領で丁度よい半熟にする。
④ 卵のかたまりを、フライパンの柄と反対側の鍋肌に寄せる。
⑤ 左手でフライパンを持ち、右手でこぶしを作って左手を何度か叩くと、卵が徐々にひっくり返り、キレイなオムレツが出来る。
ただ、間違いじゃありませんが多分これを読んだだけでは、小学生の私にフワッフワなオムレツは永遠にできなかったと思います。
私のオムレツがフワフワになったのは、コックさんの適切なアドバイスがあったからです。
ボールに卵を割り入れ、さらに卵の殻の内側についた白身を指でさらってそこに入れたコックさんは、
「ここでよ~く解きほぐすんです。かたまりが残らないぐらいよく解きほぐしてください。」
と、おっしゃいました。
そしてそれを油をひいたフライパンに入れるときも、
「フライパンは必ず強火でね、よく熱するんです。 これだけ熱しても、卵はこげませんから。 大丈夫ですから、こわがらずに強火でよくフライパンを熱して、熱くなったところで強火のまま卵を入れてください。 オムレツは強火で作るんです。」
(鉄製のフライパン)
「卵はね、外周から固まってきますから、固まってきた外周に箸を入れて(オムレツの中身、半熟スクランブルエッグ状態を)作ります。」
そして、半熟卵をフライパンの柄の反対側の端っこに寄せてかため、
左手で柄を持って、右手で拳を作って、柄を持っている左手をコンコンコンコンと叩く。
すると、あら不思議。
卵がひっくり返って、美味しいふわふわオムレツの出来上がり。なのですが、
「このフライパンの上でオムレツをひっくり返すのもね、塩を卵の代わりにして練習するといいですよ。」
もう何十年も前に見た料理番組なので、セリフの詳細は正しくないのですが、
こんな感じで、ポイントをしっかり教えてもらった私は、
小学生で技術も無かったのに、オムレツだけはフワフワに焼けるようになりました。
(もちろん、ド素人の範ちゅうで。(笑))
長くなりましたが、つまり、大切なのは手順だけではない、ということ。
それを美味しく作るのに、必要なポイントもしっかり教えて欲しい。
さて、この本。
『料理のきほん練習帳![]() 』
』
シリーズ累計35万部突破。
料理レシピ本大賞、入賞本だそうです。
(知りませんでした。(笑))
山のようにあるお料理の本の中で、売れている、その理由。
レシピが丁寧。
料理を作っているときって、意外に迷っているもの。
意識レベルにのぼる、「これどうしよう」というほどの迷いではなく、
ほんのコンマ何秒か遅れてしまうぐらいの、無意識レベルぐらいの小さな迷い。
これをなくすと、やはり時短にもなる。
細かい親切なレシピ本は、ありそうで、意外に少ないように思います。
レシピ本を書いたお料理研究家さんの料理を、再現するような気持ちで作ってみると、美味しい発見が出来るかも。
お料理上手、得意、大好きさんに、あえてお勧めしませんが、
お料理初心者さん、ご自分のお料理を一から見直したいお料理不得手さんには、分かりやすい一冊かも知れません。
定番のお料理を美味しく
お店の味版