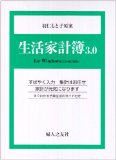婦人の友社。 家計簿のつけ方。
婦人の友社の家計簿は、主婦の友の会でつけ方を教えていただくのが、一番早く上手に家計簿をつけられる方法かと思います。
主婦の友の会は、雑誌「婦人之友」の愛読者の会で全国にあり、
毎年10~11月ごろ「家事家計講習会」という、会員さん以外の一般の方々に向けて講習会を開いています。
そこに申し込んで参加すると、家計簿のつけ方を教えていただける講習会を教えてもらえ、習うことができました。
これが本当に親切で丁寧、
つけ方はもちろん、予算のたて方を教えていただき、
さらにつけていて分からないところは、電話での相談窓口があって、無料で聞くことができます。
婦人の友社の家計簿の考案者である「婦人之友」の創刊者の羽仁もと子さんがクリスチャンで、キリスト教のボランティアや奉仕精神が息づいている団体のような雰囲気がありました。
(私は会員ではなく、詳しくは知りません。)
始めにそういう講習会などで聞いたり相談して、つけ方が分かるととても助かります。
後はだいたい自分でつけることができ、もし分からないところがでると、家計簿の電話相談窓口で質問できるので安心で、至れり尽くせりだと思いました。
さて、そんな婦人の友社の家計簿は、まず収入総額を書き、そこから引かれる税金や社会保険料などを細かく記帳。
支出は、副食費、主食費、調味料費、光熱費、住居・家具費、衣服費、教育費、交際費、教養費、娯楽費、保険・衛生費、職業費、特別費、公共費、などの費目に分けて記帳します。
(車費など、別に自分で作りたい費目があれば2つぐらい作ることも可能。)
自分が使ったお金がどの費目に入るのか迷う時は、「すぐわかる予算生活のガイド」という薄いガイドブックが付いていて、それを見るといいと思います。
よく分からなくなりがちなのがクレジットカードの扱いですが、
このつけ方に一つの正解はなく、微妙に違うそれぞれのやり方でつけることになります。
要は自分が分かるようにつける、ということですが、
私の場合は、基本的に、クレジットカードで現金が銀行口座から落ちる月のページに記帳。
これ、買った時点で記帳しないと忘れてしまうため、
クレジットカードで買い物をしたことを書くページを作り、そこに一覧として記帳しておき、
銀行からお金が落ちた月になったら、落ちる月の欄に書き写すということをしています。
ただ時々、このとおりにいかないこともあり、
(例えば、クレジットカードで副食費を支払い、買った月にどんなものを食べどんな栄養が取れているか、細目を自分で記帳しておきたいと思ったときなど。)
買った月の費目ページに記帳し(摂った食品群を書いておい)て、そのカードの買い物だけは買った月に記入する、というふうにしていることもありますが、
そこらへんは、どんなやり方でも、自分なりに自分が分かるようにつけて、
二重計上したり、抜け落ちたりすることなく、最終的に一年間のお金の使い方が正確に分かるようにしている感じです。